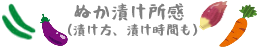昔はどこの家にもぬか漬け桶がたいていあって、わたしの祖母なども毎日、土間に置いたぬか床に片腕を根元までつっこんでかきまわしていたものだ。よく浸かったぬか漬けを噛みしめると、やさしさ、ぬくもりといったものがたちのぼってくるような気配があり、祖母の笑顔がまぶたの裏に浮かんでくるようで、ほっこりした気分になったもンである。その祖母は数年前に亡くなったが、品のある、温和で繊細な人だった。
妻の実家は兼業農家で、8反(たん)ほどの田んぼを管理しているから、代々嫁が受け継いできたとかいうぬか床がいまでも当たり前のようにある。飯時になると夏はきゅうり、冬は白菜の漬け物が大皿にてんこ盛りとなる。その味をひとことで評するなら猥雑といったところだろうか。ワイルド、といってもいい。角がたっていて、味にちょっとまとまりがない。荒々しく頑迷な義母の性格をよくあらわしていると思う。
関係あるまい、という人もいるかもしれないが、さにあらん。ぬか床に棲む微生物というものはことのほか繊細で気むずかしい生きものである。彼らにうまい漬け物をつくってもらおうというなら、日ごろから彼らのささやき声に耳を澄ませ、あたかも乳飲み子の機嫌をとるように面倒をみてやるのが正しい。それを怠っていれば、雑味の強い、しょっぱいばかりの漬け物となり果てるのは必定。不思議でもなんでもない。たかが漬け物されど漬け物――漬け物というものは、それを漬ける人間の性格や心理まで如実にあらわすもンである。
人の漬け物を食らうときなど、まるでぬか漬けの講評家のように立派な口をきくわたしではあるのだけれど、実際にやってみるとなかなか思うようにはいかぬ。年季が足りないのだから仕方なかろう、と言い訳してみても、舌打ちがやまぬ。講釈と実地は両立しがたい一例である。
天国の婆ちゃんのような立派なぬか漬け職人になるべく、日々学び経験したことを忘れぬよう書きとめておこうと立ちあげたのがこのサイト。自分自身のための備忘メモではあるが、自分のようなぬか漬け初学者の方の知見を広げるお役に立てば、これほどうれしいことはない。